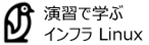Linuxコマンドの指定方法

Linuxにおけるコマンドの指定方法は、一般的に以下のように構成されます
コマンド [オプション] [引数]
1.コマンド
実行したいコマンド名を指定します。例えば、’ls‘、’cp'、’mkdir' などがコマンドとして使用されます。
2.オプション
コマンドの動作を変更したり、特定の条件で実行したりするための追加機能です。オプションは通常、’-‘(ハイフン)を前につけて指定します。例えば、’-' lや ‘-a' などが一般的なオプションの指定方法です。
3.引数
コマンドが実行される際に必要な情報やデータを指定します。例えば、’cp' コマンドでファイルをコピーする場合、コピー元ファイルやコピー先ディレクトリなどが引数として指定されます。
以下に、コマンドの指定方法の例を表にまとめます。
| コマンド | オプション | 引数 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ls | -l | (ディレクトリまたはファイル名) | ファイルやディレクトリのリスト表示(詳細表示) |
| cp | -r | (コピー元) (コピー先) | ファイルやディレクトリをコピー |
| mkdir | -p | (ディレクトリ名) | ディレクトリを作成 |
| grep | -i | (検索文字列) (ファイル名) | ファイル内の指定した文字列を検索(大文字小文字区別なし) |
| rm | -rf | (ファイルまたはディレクトリ名) | ファイルやディレクトリを削除(再帰的に削除し、確認を省略) |
これらの例では、コマンド名の後にオプションを指定し、必要に応じてその後に引数を追加してコマンドを実行しています。オプションと引数はコマンドによって異なりますが、基本的な指定方法はこのようになります。